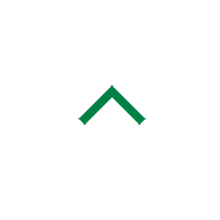Vol.31: 介護事故における民事賠償責任について(2)
-
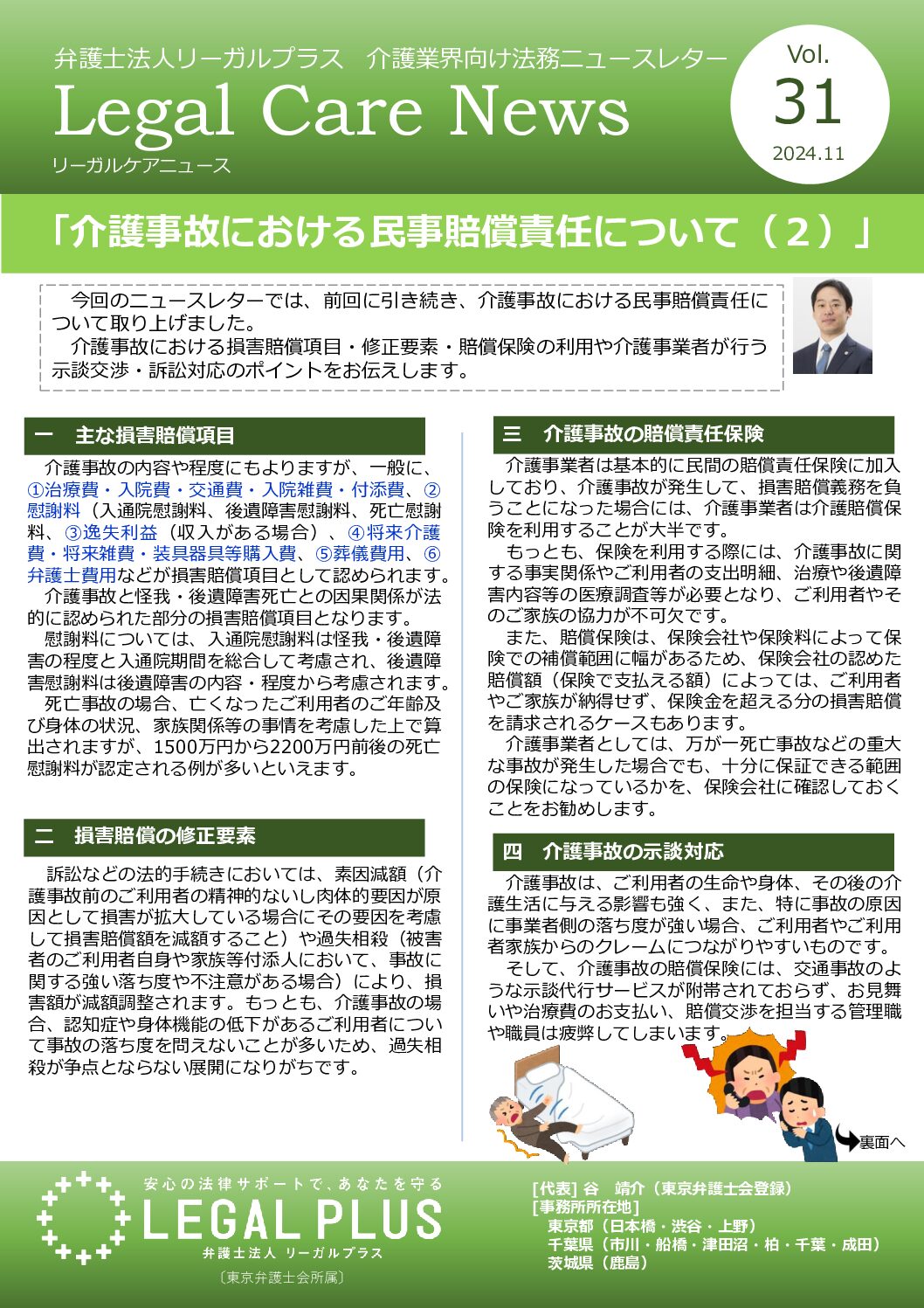
- 2024年11月 Legal Care News Vol.31 PDFで見る
今回のニュースレターでは、前回に引き続き、介護事故における民事賠償責任について取り上げました。
介護事故における損害賠償項目・修正要素・賠償保険の利用や介護事業者が行う示談交渉・訴訟対応のポイントをお伝えします。
1、主な損害賠償項目
介護事故の内容や程度にもよりますが、一般に、①治療費・入院費・交通費・入院雑費・付添費、②慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、③逸失利益(収入がある場合)、④将来介護費・将来雑費・装具器具等購入費、⑤葬儀費用、⑥弁護士費用などが損害賠償項目として認められます。
介護事故と怪我・後遺障害死亡との因果関係が法的に認められた部分の損害賠償項目となります。
慰謝料については、入通院慰謝料は怪我・後遺障害の程度と入通院期間を総合して考慮され、後遺障害慰謝料は後遺障害の内容・程度から考慮されます。
死亡事故の場合、亡くなったご利用者のご年齢及び身体の状況、家族関係等の事情を考慮した上で算出されますが、1500万円から2200万円前後の死亡慰謝料が認定される例が多いといえます。
2、損害賠償の修正要素
訴訟などの法的手続きにおいては、素因減額(介護事故前のご利用者の精神的ないし肉体的要因が原因として損害が拡大している場合にその要因を考慮して損害賠償額を減額すること)や過失相殺(被害者のご利用者自身や家族等付添人において、事故に関する強い落ち度や不注意がある場合)により、損害額が減額調整されます。もっとも、介護事故の場合、認知症や身体機能の低下があるご利用者について事故の落ち度を問えないことが多いため、過失相殺が争点とならない展開になりがちです。
3、介護事故の賠償責任保険
介護事業者は基本的に民間の賠償責任保険に加入しており、介護事故が発生して、損害賠償義務を負うことになった場合には、介護事業者は介護賠償保険を利用することが大半です。
もっとも、保険を利用する際には、介護事故に関する事実関係やご利用者の支出明細、治療や後遺障害内容等の医療調査等が必要となり、ご利用者やそのご家族の協力が不可欠です。
また、賠償保険は、保険会社や保険料によって保険での補償範囲に幅があるため、保険会社の認めた賠償額(保険で支払える額)によっては、ご利用者やご家族が納得せず、保険金を超える分の損害賠償を請求されるケースもあります。
介護事業者としては、万が一死亡事故などの重大な事故が発生した場合でも、十分に保証できる範囲の保険になっているかを、保険会社に確認しておくことをお勧めします。
4、介護事故の示談対応
介護事故は、ご利用者の生命や身体、その後の介護生活に与える影響も強く、また、特に事故の原因に事業者側の落ち度が強い場合、ご利用者やご利用者家族からのクレームにつながりやすいものです。
そして、介護事故の賠償保険には、交通事故のような示談代行サービスが附帯されておらず、お見舞いや治療費のお支払い、賠償交渉を担当する管理職や職員は疲弊してしまいます。
そのような場合、ご利用者やご家族への対応でどのような注意をしながら進めればよいか、弁護士の法的なアドバイスを受けることは有用です。
時には、死亡事故などの場合、遺族から民事訴訟を提起される事態もありますので、訴訟の場面では、介護事故の対応に詳しい弁護士へ訴訟対応を任せることも重要となります。

-
弁護士法人リーガルプラス代表弁護士 東京弁護士会所属
介護法務研究会(C-LA)代表
谷 靖介(たに やすゆき)
石川に生まれ、東京で幼少期を過ごす。1999年明治大学法学部卒業、2004年弁護士登録。日本弁護士連合会の公設事務所プロジェクトに参加し、2005年、実働弁護士ゼロ地域の茨城県鹿嶋市に赴任。翌年には年間500名以上の法律相談を担当し、弁護士不足地域での法務サービスに尽力する。弁護士法人リーガルプラスを設立し、複数の法律事務所を開設し、介護医療事業への法務支援に注力。経営者協会労務法制委員会講師を務めるなど、講演経験やメディア出演も多数。