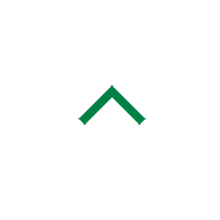2023年5月号: 労働基準法上の「労働者」とは
-

- L+PRESS 2023年5月 PDFで見る
労働基準法上の「労働者」とは
1 はじめに
先ごろ、過労自殺した男性の遺族が会社を相手取って損害賠償請求をした裁判で、請求通り約4400万円の賠償を命じる判決が言い渡されました。この事件で会社側は男性とは業務委託契約を結んでおり、男性は労働者ではなく安全配慮義務がなかったと主張しましたが、裁判所はこれを認めず、男性は労基法上の「労働者」であったと認定しました。
今回は、労働基準法が適用される「労働者」の定義についてみていきます。
2 労基法上の「労働者」と判断基準
労基法9条は労働者の定義として、「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」としています。
ある人が労基法9条の労働者にあたるかどうかは、契約の形式にかかわらず、個々の事実関係から実質的に判断されます。
実質的な判断基準は、昭和60年12月19日に当時の労働省が発表した労働基準法研究会報告に示されています。具体的には、①使用者の指揮監督の下で労働をし、②労務の対償として報酬を受領していること(二つを合わせて「使用従属性」といいます。)が求められます。
3 「指揮監督下の労働」の判断基準
指揮監督下の労働といえるかどうかの判断基準としては、
- ・仕事の依頼や業務指示に対する諾否の自由があるか
- ・業務内容、遂行方法について指揮命令があるか
- ・命令や依頼により通常予定される業務以外の業務に従事することがあるか
- ・業務場所、業務時間に拘束があるか
- ・本人に代わって他者が労務提供すること、本人の判断で補助者を使うことが認められているか
が挙げられています。
4 「報酬の労務対償性」の判断基準
労基法11条は賃金の定義を、「名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」としています。
報酬が賃金であるかどうかで使用従属性を判断できるものではありませんが、報酬の性格から使用従属性が補強されることはあります。たとえば、報酬が時間給を基礎としている(労働の結果によって差が生じないか少ない)、欠勤時に応分の報酬が控除される、残業時に通常の報酬と別の手当が支給される、などです。
5 補強要素
その他、労働者かどうかを判断する際の補強要素として、たとえば、
- ・機械や器具の負担関係(どんな機械や器具か、その量や価値など)
- ・報酬の額(同様の業務に従事している正規従業員と比較して著しく高額でないか)
- ・業務遂行上の損害に対する責任を負うか
- ・独自の商号使用が認められているか
- ・他社の業務に従事することを制約されているか、または事実上困難であるか
- ・報酬に生活保障的な要素があるか、その程度(報酬の固定給部分があるかなど)
- ・選考過程が正規従業員の場合と同様であるか
- ・報酬が給与所得として源泉徴収されているか
- ・服務規律、労働保険、退職金制度、福利厚生などが適用されているか
などが挙げられます。
6 おわりに
以上が労基法上の労働者性の判断基準となります。雇用契約でなく業務委託契約を締結する際は以上の点に注意し、実質的に労働者であると指摘されることのないよう慎重に契約内容を吟味し、かつ業務委託を実施していく必要があります。

-
【東京法律事務所】
所属弁護士:若松 俊樹(わかまつ としき)- プロフィール
- 東京大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了後、弁護士登録以降東京で3年半、茨城県水戸市で6年半強ほど一般民事や企業法務などの分野で執務。現在は東京事務所で、交通事故、労災事故、離婚・不貞問題などを中心に活動を行う。趣味は読書や音楽鑑賞、好きな言葉は「鬼手仏心」、「神は細部に宿る」。
交通事故解決事例
Xさんは交差点を右折のため停車していたところ、後方から加害者が運転する車両に追突されてしまい、頚椎捻挫及び腰椎捻挫のけがを負いました。Xさんは懸命に通院を継続して治療を行いましたが、残念ながら首や腕に痺れが残ってしまいました。
【事前認定とは】
交通事故によるけがの痛みや痺れ等が残ってしまった場合、被害者は、加害者が加入する自賠責保険会社に対し、後遺障害等級の認定申請をすることができます。申請に必要な書類を被害者が自ら集めて申請手続を行うことを被害者請求と言い、加害者側の任意保険会社を介して申請手続を行うことを事前認定と言います。Xさんは、事前認定の方法で後遺障害申請を行いましたが、残念ながら非該当、すなわち、後遺障害に該当しないという判断になってしまいました。
【異議申立手続】
一度非該当の判断が出た場合、新たな資料を提出しない限りは判断が覆ることはほぼありませんが、Xさんからご説明を受けた事故状況、通院期間、治療内容、現在の自覚症状等に鑑み、異議申立を行うこととしました。
異議申立にあたり、Xさんが痺れを感じる箇所のMRI画像を取得したほか、本件事故によってXさんが身体に受けた衝撃の度合いを立証するため、Xさんのお車の破損状況を表す資料(事故車の写真や修理見積等)を取得し、これまでの通院経過や治療内容等から、Xさんの痛みが事故当初から一貫して継続していたこと等を主張して異議申立てを行った結果、Xさんは14級9号の後遺障害を獲得することができました。
【示談交渉】
交通事故により傷害を負った場合、①治療費、②通院交通費、③休業損害、④入通院慰謝料を請求することができますが、後遺障害が認定された場合には、さらに、認定された後遺障害に応じた⑤慰謝料及び⑥逸失利益(後遺障害が残ることによって今後見込まれる減収を算定したもの)を請求することができますので、後遺障害が認定されるか否かは被害者が獲得できる金額にダイレクトに影響します。後遺障害14級が認定されたXさんは、示談交渉の結果、約300万円の示談金を獲得することができました。
【おわりに】
交通事故によるおケガの治療を続けても、残念ながら、完治せず、痛みや痺れ等が残ってしまうことがあります。また、後遺障害認定の壁は高く、非該当の結果になってしまう被害者の方が大勢いらっしゃいます。しかし、適切な治療を、適切な頻度で、適切な期間行ったにもかかわらず、日常生活に支障をきたすほどの痛みや痺れが残るような場合には、後遺障害が認定される可能性があります。一度、後遺障害申請が非該当となってしまった場合でも、弁護士のサポートにより適切な主張、や証拠を集めて異議申立を行うことにより、非該当の結果を覆すことができるかもしれません。交通事故で後遺障害結果に疑問をお持ちの方は、ぜひ、弊所の法律相談にお越しください。

-
【船橋法律事務所】
所属弁護士:今福 康裕(いまふく やすひろ)- プロフィール
- 立教大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。弁護士登録以前は、裁判所書記官として民事・刑事の裁判事務を務める。現在は船橋事務所で、交通事故、個人破産、刑事弁護などを中心に、困っている人を助け、寄り添った仕事をしたいという想いのもと活動を行う。趣味は映画鑑賞や格闘技観戦、好きな言葉は「おもしろきこともなき世をおもしろく」。