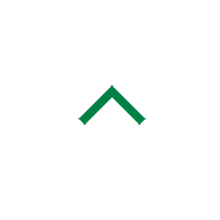2024年7月号: LGBTQ等への対応の在り方
-
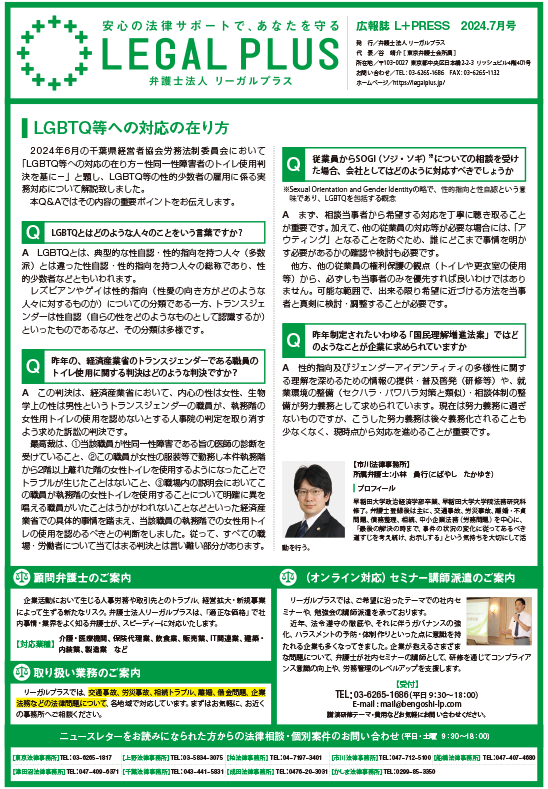
- L+PRESS 2024年7月 PDFで見る
LGBTQ等への対応の在り方
2024年6月の千葉県経営者協会労務法制委員会において「LGBTQ等への対応の在り方−性同一性障害者のトイレ使用判決を基に−」と題し、LGBTQ等の性的少数者の雇用に係る実務対応について解説致しました。
本Q&Aではその内容の重要ポイントをお伝えします。
LGBTQとはどのような人々のことをいう言葉ですか?
A LGBTQとは、典型的な性自認・性的指向を持つ人々(多数派)とは違った性自認・性的指向を持つ人々の総称であり、性的少数者などともいわれます。
レズビアンやゲイは性的指向(性愛の向き方がどのような人々に対するものか)についての分類である一方、トランスジェンダーは性自認(自らの性をどのようなものとして認識するか)といったものであるなど、その分類は多様です。
昨年の、経済産業省のトランスジェンダーである職員のトイレ使用に関する判決はどのような判決ですか?
A この判決は、経済産業省において、内心の性は女性、生物学上の性は男性というトランスジェンダーの職員が、執務階の女性用トイレの使用を認めないとする人事院の判定を取り消すよう求めた訴訟の判決です。
最高裁は、①当該職員が性同一性障害である旨の医師の診断を受けていること、②この職員が女性の服装等で勤務し本件執務階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになったことでトラブルが生じたことはないこと、③職場内の説明会においてこの職員が執務階の女性トイレを使用することについて明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれないことなどといった経済産業省での具体的事情を踏まえ、当該職員の執務階での女性用トイレの使用を認めるべきとの判断をしました。従って、すべての職場・労働者について当てはまる判決とは言い難い部分があります。
従業員からSOGI(ソジ・ソギ)※についての相談を受けた場合、会社としてはどのように対応すべきでしょうか
※Sexual Orientation and Gender Identityの略で、性的指向と性自認という意味であり、LGBTQを包括する概念
A まず、相談当事者から希望する対応を丁寧に聴き取ることが重要です。加えて、他の従業員の対応等が必要な場合には、「アウティング」となることを防ぐため、誰にどこまで事情を明かす必要があるかの確認や検討も必要です。
他方、他の従業員の権利保護の観点(トイレや更衣室の使用等)から、必ずしも当事者のみを優先すれば良いわけではありません。可能な範囲で、出来る限り希望に近づける方法を当事者と真剣に検討・調整することが必要です。
昨年制定されたいわゆる「国民理解増進法案」ではどのようなことが企業に求められていますか
A 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供・普及啓発(研修等)や、就業環境の整備(セクハラ・パワハラ対策と類似)・相談体制の整備が努力義務として求められています。現在は努力義務に過ぎないものですが、こうした努力義務は後々義務化されることも少なくなく、現時点から対応を進めることが重要です。

-
【市川法律事務所】
所属弁護士:小林 貴行(こばやし たかゆき)- プロフィール
- 早稲田大学政治経済学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了後、弁護士登録(千葉県弁護士会)。主に、交通事故、労災事故、債務整理、相続、中小企業法務(労務問題)を中心に、「最後の解決の時まで、事件の状況の変化に従ってあるべき道すじを考え続け、お示しする」という気持ちを大切にして活動を行う。
交通事故解決事例
1 事案の概要
Ⅹさんがバイクで優先道路を走行中、非優先道路から合流しようとしてきた相手方車両と衝突し、頚椎捻挫などの怪我を負いました。Ⅹさんは、事故当時、個人事業主として配送業を営んでいましたが、この事故による怪我の痛みや療養のため、仕事にも支障が生じるようになってしまいました。
2 自営業の休業損害の考え方
怪我によって休業または不十分な稼働を余儀なくされ、本来得られたはずの利益が得られなかった場合、この損害を休業損害といいます。そして、給与所得者の場合は、休業損害証明書を勤務先に作成してもらうことでいくらの減収が生じているかは明らかとなるため、休業期間が長期に渡らなければ、休業損害の金額が争いにならずに済むことも少なくありません。
一方、自営業者の場合、給与所得者のように休業損害証明書を使うことができません。このため、どのような資料からどのように計算をして休業損害の額を決めるか、給与所得者の場合と比較して争いになることが多くなります。
この点、確立された計算方法はありませんが、実務上は、事故前年度の確定申告書などを参考にして、次のような計算式で損害を求めることが多いです。
(事故前年度所得金額+固定経費)×寄与率÷365日×休業日数
しかしながら、この計算式によることを前提としても、ここでいう固定経費はいくらか、寄与率はどのくらいか、休業日数は何日とすべきかなど、さらに細かく争いが生じることとなります。
3 本件の経過
Ⅹさんは、弁護士費用特約に加入されていたため、本件事故に遭われてすぐ、事故対応全般について弁護士に依頼したいと当事務所へいらっしゃいました。保険会社とのやり取りなどは弁護士が対応し、その間Ⅹさんには治療に専念していただくとともに、休業損害の計算のために必要な資料の収集をお願いしました。
Xさんから提供を受けた資料をもとに、弁護士が適切な休業損害を計算し、相手方保険会社に対してその支払いを求めました。
それと同時に、弁護士がどのような計算方法で金額を出したか、なぜそのような方法によることが適切といえるか、相手方保険会社に対して丁寧に説明を行いました。
その結果、Xさんの休業損害については当方請求額全額の支払いを受けることができました。
4 おわりに
交通事故に遭われた方々においては、仕事ができない分の損害が適切に支払われるか分からず多大な不安を感じられることかと存じます。特に自営業の場合には、上記のように計算方法が確立されていない実態から、不適切な金額で交渉が進んでしまう可能性も多くございます。ご不明な点がございましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

-
【柏法律事務所】
所属弁護士:宇野 浩亮(うの こうすけ)- プロフィール
- 一橋大学法学部法律学科卒業、一橋大学法科大学院修了。弁護士登録後は柏法律事務所に所属し、主に、交通事故、労働事件、相続、離婚・不貞問題、中小企業法務(労務問題)を中心に活動を行い、ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、信頼される関係をしっかりと構築しながら解決に向けた活動を行う。好きな言葉は「一期一会」。