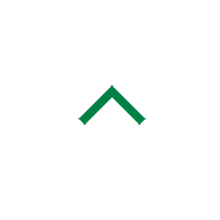2024年10月号: 遺言書が無くても相続人以外の人が遺産を取得できる場合があります
-

- L+PRESS 2024年10月 PDFで見る
遺言書が無くても相続人以外の人が遺産を取得できる場合があります
1 はじめに
大事な人が亡くなったあとの財産の権利者を確定させる手続きが遺産分割です。
遺産を取得する人については、遺言書があれば遺言書に従い、遺言書が無ければ法律に従い相続人が取得します。法律は、配偶者と、①子、②親、③兄弟の順番で相続人になることを定めています。対象者以外の人と遺産を分けることはできますが、贈与となって税金が発生する場合があるため注意が必要です。
逆に、生前の被相続人のために貢献したのに、相続人でないために遺産分割協議に参加できず、その貢献を遺産の分配に反映させられない場合が、従前問題となっていました。
この問題を解消する法改正が平成30年に行われ、相続人以外の人でもその貢献分の分配を請求できる「特別の寄与(特別寄与料制度)」が規定されました。改正から時間が経っていますが、あまりこの制度が知られてないように思いますので、今回改めてご紹介致します。
2 特別寄与料とは
(1)請求できる人
特別寄与料は、遺産分割の手続きではありません。特別寄与料が認められるための次の3つの要件全てを満たす人が相続人に対して請求するものです。
- 相続人ではない親族であること
典型的には子の配偶者(Ex.長男の嫁)などが該当します。 - 無償で療養看護その他の労務を提供したこと
被相続人の介護を無償で行う場合等が該当します。 - ②により被相続人の財産が維持または増加したこと
その貢献により被相続人の財産が増加もしくは減少しなかった等の結果が必要となります。例えば、要介護2の義母を介護したことでヘルパー利用にかかる費用を抑えられた場合、財産の減少防止に貢献したといえる場合があります。
その防止分を金銭換算して、特別寄与料として請求することができます。
(2)請求のやり方
特別寄与料の請求の相手方は、相続人です。相続人は、相続分に応じて特別寄与料を支払う義務を負います。特別寄与料の請求は、話し合いでも行えますが、まとまらない場合は、裁判所の調停もしくは審判手続により特別寄与料が定められます。
特別寄与料の調停審判の申立てには期間制限があり、相続開始と相続人を知った時から6か月もしくは相続開始から1年を過ぎると申立てができなくなります。
特別寄与料の調停審判では、貢献内容の証拠が必要となります。毎日の介護日誌をつけるなどして、どのような活動をどのくらいの時間行ったのか記録しておくことが重要といわれています。
3 さいごに
今回は、特別寄与料の制度をご紹介させていただきました。相続に関しては、他にも相続人間の不公平是正に資する制度があります。お悩みの際には、使えそうな制度が無いか探してみるか、弁護士などの専門家に相談いただくことをおすすめ致します。

-
【東京法律事務所】
所属弁護士:藥師寺 孝亮(やくしじ こうすけ)- プロフィール
- 早稲田大学商学部卒業、日本大学法科大学院修了。民間企業に勤務していたが、一念発起して弁護士を目指す。現在は東京法律事務所に所属し、主に相続を中心に活動を行う。「ご相談者様・ご依頼者様に笑顔を取り戻してもらいたい。」という思いを大切に、少しでも良い未来に向かっていただけるよう、知恵を絞り、行動するよう心がけている。好きな言葉は「人事を尽くして天命を待つ」。
交通事故解決事例
Aさんは、比較的狭い道路をバイクで走行していたところ、丁字路を右折する自動車が見えたため、丁字路の手前で停車して右折車が通りすぎるのを待っていました。しかし、Aさんは右折し終わった自動車に接触されてしまい、幸いAさんに怪我はありませんでしたが、Aさんの乗っていたバイクには大きな傷がついてしまいました。相手方は、Aさんの停車位置が悪かったとして過失割合3:7を主張しており、過失割合が問題となりました。
1 過失割合の決め方
過失割合を判断するにあたって、実務上、最初に参考にする 資料は『別冊判例タイムズ NO.38』(以下、「判タ」といい ます。)です。判タは、過去の裁判例等から典型的な交通事故を 類型化し、事故態様に応じて一応の目安となる基本的な過失割 合を記載したものです。また、事故態様によっては、基本的な過失割合を左右する修正要素なども記載されています。そのため、典型的な事故については、判タの基本的な過失割合や修正 要素をもとに、事案に応じて過失割合を決めていきます。
また、類型化できない非典型事故については、実際の裁判例 等を調査し、そこに修正を加えながら過失割合を決めていくこ ともあります。
過失割合は合計で10(100%)にならないこともあり、0:9 等の場合を片賠(片側賠償)といいます。
2 解決までの経緯
相手方は、Aさんの停車位置が道路の中心に近い場所であり、停車位置が悪かったことが本件事故の原因であるとして、当初3:7という過失割合を主張していました。
しかし、3:7という根拠についてはAさんには開示されておらず、Aさんとしては納得ができない状態でした。
そこで、弁護士が0:10を主張しつつ、相手方の主張の根拠の提出を求めました。相手方から提出された根拠となる裁判例を見る限りでは、過失割合は最大でも2:8だと考えられました。
一方、Aさんのバイクの修理費用は安価であり、仮に2:8だとしても相手方の損害額の方が高くなってしまうという状況でした。
Aさんは、自らに過失があるとは思えないけれども、過失割合はある程度までなら譲歩して早く解決し、可能であれば相手方には損害額を支払いたくないというご意向でしたので、弁護士から片賠を提案しました。
その結果、無事0:8の過失割合で和解することができ、Aさんには無事にバイク修理費用の8割が支払われました。
3 おわりに
Aさんのように、相手方から納得のいかない過失割合を主張されてお困りの方もいらっしゃると思います。
相手方保険会社からの過失割合の主張が適正なものであるかご不安がある方は、是非一度当事務所にご相談ください。

-
【成田法律事務所】
所属弁護士:常世 紗雪(とこよ さき)- プロフィール
- 中央大学法学部法律学科卒業、一橋大学法科大学院修了。弁護士登録後は成田法律事務所に所属し、主に、交通事故、労働事件、離婚・不貞問題を中心に活動を行う。コミュニケーションを疎かにせず、ご依頼者様に心からご納得・ご理解いただけるように説明することを心がけている。好きな言葉は「進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む」。