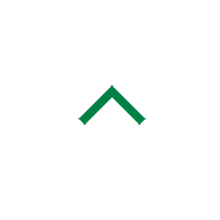2024年11月号: 労働時間管理の法的リスクと対策
-
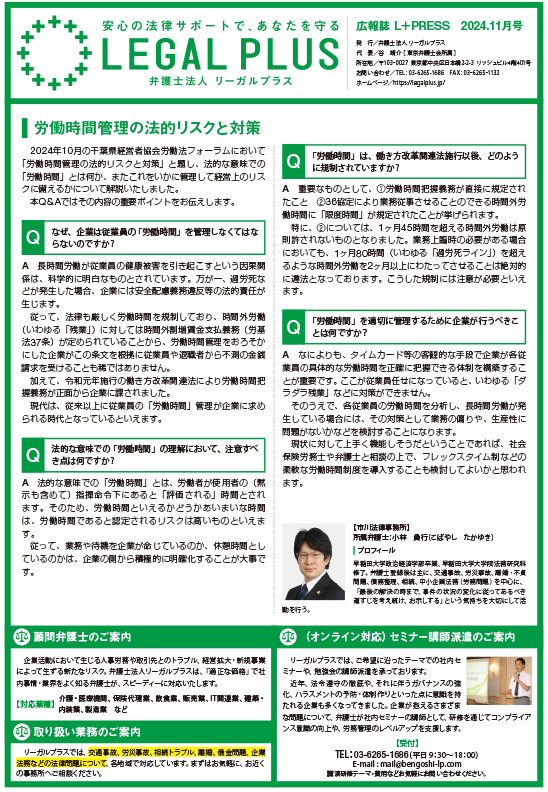
- L+PRESS 2024年11月 PDFで見る
労働時間管理の法的リスクと対策
2024年10月の千葉県経営者協会労働法フォーラムにおいて「労働時間管理の法的リスクと対策」と題し、法的な意味での「労働時間」とは何か、またこれをいかに管理して経営上のリスクに備えるかについて解説いたしました。
本Q&Aではその内容の重要ポイントをお伝えします。
なぜ、企業は従業員の「労働時間」を管理しなくてはならないのですか?
A 長時間労働が従業員の健康被害を引き起こすという因果関係は、科学的に明白なものとされています。万が一、過労死などが発生した場合、企業には安全配慮義務違反等の法的責任が生じます。
従って、法律も厳しく労働時間を規制しており、時間外労働(いわゆる「残業」)に対しては時間外割増賃金支払義務(労基法37条)が定められていることから、労働時間管理をおろそかにした企業がこの条文を根拠に従業員や退職者から不測の金銭請求を受けることも稀ではありません。
加えて、令和元年施行の働き方改革関連法により労働時間把握義務が正面から企業に課されました。
現代は、従来以上に従業員の「労働時間」管理が企業に求められる時代となっているといえます。
法的な意味での「労働時間」の理解において、注意すべき点は何ですか?
A 法的な意味での「労働時間」とは、労働者が使用者の(黙示も含めて)指揮命令下にあると「評価される」時間とされます。そのため、労働時間といえるかどうかあいまいな時間は、労働時間であると認定されるリスクは高いものといえます。
従って、業務や待機を企業が命じているのか、休憩時間としているのかは、企業の側から積極的に明確化することが大事です。
「労働時間」は、働き方改革関連法施行以後、どのように規制されていますか?
A 重要なものとして、 ①労働時間把握義務が直接に規定されたこと ②36協定により業務従事させることのできる時間外労 働時間に「限度時間」が規定されたことが挙げられます。
特に、②については、1ヶ月45時間を超える時間外労働は原 則許されないものとなりました。業務上臨時の必要がある場合 においても、1ヶ月80時間(いわゆる「過労死ライン」)を超えるような時間外労働を2ヶ月以上にわたってさせることは絶対的に違法となっております。こうした規制には注意が必要といえます。
「労働時間」を適切に管理するために企業が行うべきことは何ですか?
A なによりも、タイムカード等の客観的な手段で企業が各従業員の具体的な労働時間を正確に把握できる体制を構築することが重要です。ここが従業員任せになっていると、いわゆる「ダラダラ残業」などに対策ができません。
そのうえで、各従業員の労働時間を分析し、長時間労働が発生している場合には、その対策として業務の偏りや、生産性に問題がないかなどを検討することになります。
現状に対して上手く機能しそうだということであれば、社会保険労務士や弁護士と相談の上で、フレックスタイム制などの柔軟な労働時間制度を導入することも検討してよいかと思われます。

-
【市川法律事務所】
所属弁護士:小林 貴行(こばやし たかゆき)- プロフィール
- 早稲田大学政治経済学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。弁護士登録後は主に、交通事故、労災事故、離婚・不貞問題、債務整理、相続、中小企業法務(労務問題)を中心に、「最後の解決の時まで、事件の状況の変化に従ってあるべき道すじを考え続け、お示しする」という気持ちを大切にして活動を行う。
交通事故解決事例
Kさんは、横断歩道上を歩行中にタクシーに衝突され、右足をタイヤに轢かれたことにより、右足開放性粉砕骨折の重傷を負いました。Kさんは、2回の手術に耐え、約10か月にわたり懸命に治療を継続しましたが、右足に可動域制限の後遺障害(事前認定12級)が遺りました。加害者側保険会社から、後遺障害12級を前提に示談金の提示があったため、このまま示談していいのか不安を抱かれ、弊所へ法律相談にお越しになられました。
事前認定の結果を検討中に後遺障害診断書の誤りを発見
後遺障害認定の申請には、事前認定と被害者請求の2種類があり、加害者側の保険会社が申請を行う場合を事前認定と言います。被害者請求と異なり、被害者が申請手続をしなくていい点がメリットとされますが、加害者側保険会社がどのような資料を付けて申請したか分からないため、事前認定結果に誤りがないか、注意が必要となります。
Kさんの事前認定結果に誤りがないか、より上位の等級が認められる余地がないかを検討する過程で、後遺障害診断書に不自然な点があることに気が付きました。Kさんがケガをしたのは右足なので、左足と比べて、右足の可動域に制限が生じていましたが、一つだけ、右足の方が左足より可動域の検査結果が良い項目がありました。他の検査項目と比べて明らかにおかしいと思い、後遺障害診断書を作成した病院に確認したところ、左右の計測結果を誤って逆に記載していたことが判明しました。医師が作成した診断書にまさか間違いがあるとは信じ難いですが、後遺障害診断書の内容は必ずチェックすることが重要です。
事前認定に対する異議申立てと示談交渉
病院に後遺障害診断書の誤りを修正してもらい、事前認定に対する異議申立てを行った結果、無事、後遺障害等級が12級から9級(他の等級と併合)へと変更されました。
その後、加害者側保険会社との交渉の結果、弁護士介入前の示談提案金約530万円から、最終的には約1200万円で示談を成立させることができました。
Kさんには大変満足していただけたので、弁護士冥利に尽きると思う一方で、後遺障害診断書にたった一つの記載間違いがあるだけで、交通事故の被害者は取り返しのつかない損害を被る恐れがあると考えると、事前認定結果の検討及び後遺障害診断書のチェックの重要さを改めて痛感しました。
最後に
医師といえども人間である以上、間違いはあり得ます。しかし、後遺障害診断書はその後の後遺障害申請の結果を左右する大変重要な診断書であり、万に一つでも誤りはあってはいけません。Kさんのように明らかな誤記は珍しいですが、他の事例でも、本来やらなければならない検査が行われていない、必要な記載が漏れているなど、後遺障害診断書に誤りがあることは珍しくありません。また、事前認定の結果も、必ずしも正しい認定結果とは限りません。事前認定結果を前提とした示談金の提案を受けた場合でも、その場で提案に承諾せず、まずは弁護士へご相談ください。

-
【市川法律事務所】
所属弁護士:今福 康裕(いまふく やすひろ)- プロフィール
- 立教大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。弁護士登録以前は、裁判所書記官として民事・刑事の裁判事務を務める。現在は市川事務所で、交通事故、個人破産、刑事弁護などを中心に、困っている人を助け、寄り添った仕事をしたいという想いのもと活動を行う。趣味は映画鑑賞や格闘技観戦、好きな言葉は「おもしろきこともなき世をおもしろく」。