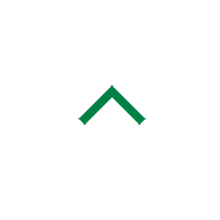2024年12月号: 事業場外みなし労働時間制の適用のあり方について
-

- L+PRESS 2024年12月 PDFで見る
事業場外みなし労働時間制の適用のあり方について
1 はじめに
今年4月、ある事業場外みなし労働時間制の適用をめぐり、最高裁が高裁判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。同制度の解釈適用に大きな影響を与える判断となるため、今回はこの点を考えてみたいと思います。
2 事案と判決の概要
本件は、外国人技能実習に係る管理団体の元指導員が事業場外で従事した業務につき、事業場外みなし労働時間制が適用されるかが争点の一つとなりました。
高裁は、①元指導員の業務日報を通じて団体が報告を受けており、各所に確認も可能であって、業務日報の記載の正確性がある程度担保されていた、②団体が業務日報の記載を前提に残業手当を支払う場合もあり、業務日報の正確性を前提としていたとして、事業場外みなし労働時間制は適用されないとの判断を示しました。
これに対し最高裁は、①の各所への確認については一般的な指摘に過ぎず、その現実的な可能性や実効性が具体的に明らかでないとしました。②についても、残業手当を支払っていたのは業務日報のみによらず労働時間を把握できた場合に限られるという団体の主張の当否が十分に検討されていないとして、高裁に差し戻しました。
3 分析と検討、求められる対応
事業場外みなし労働時間制の要件である「労働時間を算定し難いとき」の判断のためには、①業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、②使用者と被用者との間の業務に関する指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮する必要があります(最判平成26年1月24日・阪急トラベルサポート事件)。本件最高裁判決は上記判断基準に則りつつ、高裁の事実認定及び具体的検討の不備を指摘したものといえます。
こうした判断基準や本件判決を踏まえ、事業場外みなし労働時間制を導入する場合、注意すべき点を考えてみましょう。まず、対象労働者の業務が事業場外で行われ、かつ業務の性質上会社による厳格な時間管理、業務管理がそぐわないことが必要となってきます。またこれと関連し、業務管理やスケジュール管理について会社が対象労働者に相応の裁量を持たせることも重要となります。本件判決でも、元指導員の業務が多岐にわたることや、元指導員が自らスケジュール管理をしており休憩時間変更や直行直帰も自らの判断で許容されていたことが指摘されています。
この点については、平成30年2月22日付、厚生労働省の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入および実施のためのガイドライン」も参考となります。同ガイドラインでは、テレワークが労働時間を算定し難いといえるためには、①情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態に置くこととされていないこと、②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないことが必要であるとしており、テレワーク以外の事業場外労働にも応用できる要件であると考えられます。以上からしますと、事業場外みなし労働時間制の適用には、対象業務の詳細な分析と慎重な制度設計が欠かせないといえるでしょう。

-
【柏法律事務所】
所属弁護士:若松 俊樹(わかまつ としき)- プロフィール
- 東京大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了後、弁護士登録以降東京で6年、茨城県水戸市で6年半強ほど一般民事や企業法務などの分野で執務。現在は柏事務所で、交通事故、労災事故、離婚・不貞問題などを中心に活動を行う。趣味は読書や音楽鑑賞、好きな言葉は「鬼手仏心」、「神は細部に宿る」。
交通事故解決事例
Aさんは、交通事故により、左手首の骨折の傷害を負い、約2年間病院で治療を継続しました。しかし、Aさんの左手首には、不正癒合(骨がズレてくっついてしまうこと)により強い痛みが残ってしまいました。
Aさんは、治療終了後、体調があまり良くなかったこと、仕事が忙しかったことなどから、保険会社とあまり連絡を取ることができず、示談ができないまま、治療終了から約2年の月日が経過してしまいました。そうしたところ、Aさんの自宅に裁判所から郵便物が届き、Aさんが中を見てみると、加害者がAさんに対し「債務不存在確認訴訟」を提起したという内容の書類が入っていました。
裁判所から突然このような書類が届いたAさんは、とても驚き、慌てて法律相談にいらっしゃいました。
1 債務不存在確認訴訟とは?
裁判は、通常、金銭の支払いを求めるなど、「請求をする側」が起こすものです。しかし、債務不存在確認訴訟は、通常の裁判とは異なり、「請求をされる側」が、金銭を(これ以上)支払う必要はないことなどを確定させるために起こすものです。
交通事故の場合、①被害者と保険会社との主張に大きな開きがあるため、示談ができず、月日が経過してしまった場合、②Aさんのように、被害者が保険会社とあまり連絡をできておらず、月日が経過してしまった場合などに、債務不存在確認訴訟を提起されることがあります。
2 法律相談
Aさんから相談を受けた弁護士は、Aさんが賠償金を獲得できる可能性があること、裁判所からの連絡をこのまま放置をしてしまうと、その賠償金が獲得できなくなってしまうことなどを説明し、Aさんから依頼を受けることにしました。
3 裁判
弁護士は、Aさんから依頼を受けた直後、すぐに裁判所に必要書類を提出し、裁判対応を開始しました。
弁護士は、裁判の序盤では、Aさんの左手首には、交通事故によって、強い痛みが残ってしまっていることから、後遺障害の認定手続をした上で、賠償額の議論をするべきであると主張し、裁判官もそれを承諾しました。弁護士は、必要書類を収集した上で、自賠責保険会社に対し、後遺障害の認定手続を申請したところ、後遺障害等級第12級が認定され、まずは自賠責保険会社から224万円が支払われました。
その後、被害者側及び加害者側の弁護士が主張・立証を尽くし、裁判所から、自賠責保険金224万円のほかに730万円を支払うとする和解案が提示され、被害者側も加害者側もこれに応じることとし、裁判は終結しました。
4 おわりに
Aさんは、弁護士に依頼をし、裁判で争った結果、合計954万円の賠償金を獲得することができました。
仮にAさんが弁護士に相談せず、裁判所からの連絡を放置してしまっていた場合には、賠償金を獲得できなくなってしまったという結末もあり得ました。
債務不存在確認訴訟が提起されるケースはそこまで多いわけではありませんが、示談交渉が上手くいかない場合には、早めに弁護士に相談し、解決を目指すことをおすすめします。

-
【船橋法律事務所】
所属弁護士:西池 峻矢(にしいけ しゅんや)- プロフィール
- 早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。弁護士登録以降、「自身が勉強した法律を使って、法的な紛争で苦しんでいる人々を助けてあげたい」という気持ちを胸に、交通事故や一般民事、家事事件などの分野で活動を行う。趣味は野球やラグビーなどのスポーツ観戦、好きな言葉は「意志あるところに道は開ける」。