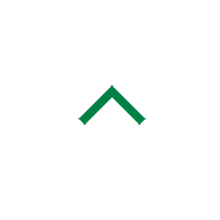2024年1月号: 法改正「育児介護休業法等改正」
-
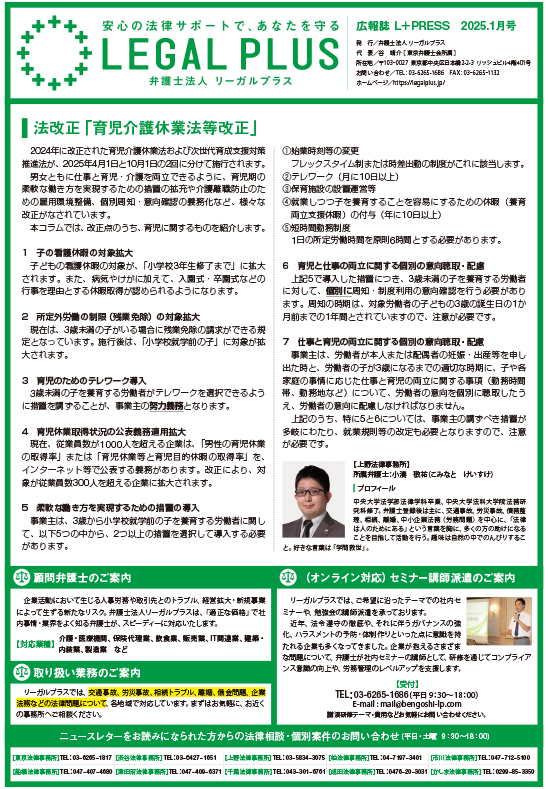
- L+PRESS 2024年1月 PDFで見る
法改正「育児介護休業法等改正」
2024年に改正された育児介護休業法および次世代育成支援対策推進法が、2025年4月1日と10月1日の2回に分けて施行されます。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化など、様々な改正がなされています。
本コラムでは、改正点のうち、育児に関するものを紹介します。
1 子の看護休暇の対象拡大
子どもの看護休暇の対象が、「小学校3年生修了まで」に拡大されます。また、病気やけがに加えて、入園式・卒園式などの行事を理由とする休暇取得が認められるようになります。
2 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
現在は、3歳未満の子がいる場合に残業免除の請求ができる規定となっています。施行後は、「小学校就学前の子」に対象が拡大されます。
3 育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となります。
4 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
現在、従業員数が1000人を超える企業は、「男性の育児休業の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を、インターネット等で公表する義務があります。改正により、対象が従業員数300人を超える企業に拡大されます。
5 柔軟な働き方を実現するための措置の導入
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの中から、2つ以上の措置を選択して導入する必要があります。
- 始業時刻等の変更
フレックスタイム制または時差出勤の制度がこれに該当します。 - テレワーク(月に10日以上)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(年に10日以上)
- 短時間勤務制度
1日の所定労働時間を原則6時間とする必要があります。
6 育児と仕事の両立に関する個別の意向聴取・配慮
上記5で導入した措置につき、3歳未満の子を養育する労働者に対して、個別に周知・制度利用の意向確認を行う必要があります。周知の時期は、対象労働者の子どもの3歳の誕生日の1か月前までの1年間とされていますので、注意が必要です。
7 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項(勤務時間帯、勤務地など)について、労働者の意向を個別に聴取したうえ、労働者の意向に配慮しなければなりません。
上記のうち、特に5と6については、事業主の講ずべき措置が多岐にわたり、就業規則等の改定も必要となりますので、注意が必要です。

-
【上野法律事務所】
所属弁護士:小湊 敬祐(こみなと けいすけ)- プロフィール
- 中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院法務研究科修了。弁護士登録後は主に、交通事故、労災事故、債務整理、相続、離婚、中小企業法務(労務問題)を中心に、「法律は人のためにある」という言葉を胸に、多くの方の助けになることを目指して活動を行う。趣味は自然の中でのんびりすること。好きな言葉は「学問救世」。
交通事故解決事例
Aさんはバスに乗車していたところ、運転手が急ブレーキをかけたことにより車内で転倒し、怪我をしました。翌日に病院にて診察を受けたところ、頚椎捻挫・左中指、環指捻挫及び右膝挫傷等の診断を受けました。その後、Aさんは約8か月にわたり治療を継続しましたが、後頭部痛や左上肢のしびれ等が残ってしまいました。そのため、事前認定(加害者が加入する保険会社に手続を一任する申請方法)により後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害は非該当との結果を受けました。Aさんはかかる結果は妥当なものであるのか疑問に感じ、法律相談にいらっしゃいました。
1 後遺障害の認定とは
「後遺障害」とは、当該症状が交通事故が原因であると医学的 に証明されるとともに労働能力の低下が認められ、自賠責保険 の等級に該当するものと定義されております。後遺障害が残っ てしまった場合には、かかる後遺障害の等級を認定してもらう 必要があります。後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構の 自賠責調査事務所という機関で行っております。
2 申請結果に不満がある場合
後遺障害の申請結果に不満がある場合には、自賠責保険に対する異議申立てという方法により、再度判断を受けることが可能です。回数制限等はありませんが、判断を覆すためには主張と根拠となる資料を揃えて行う必要があり、損害保険料率算出機構の体裁上、基本的には1回目の異議申立てが重要となります。
また、その他にも裁判外紛争処理機関(ADR)への申請や裁判(訴訟提起)による方法もあります。もっとも、実務上は自賠責による異議申立てを第1に行うことが多いです。
3 本件の帰結
Aさんが通院されていた医療機関から医療記録(カルテや画像等)を取得し、精査した上で前述の異議申立てを行いました。
その結果、受傷部位の全てではないものの、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。
その後、相手方保険会社と交渉にて合計約254万円での示談をすることができ、Aさんも大変満足されておりました。
4 最後に
Aさんと同様に交通事故に遭い、むち打ちの怪我を負い治療を終了したものの痛みが残っているといういわゆる「後遺症」はあるものの「後遺障害」であるとは認定されないというケースは少なくありません。異議申立て等で認定結果を覆すことは困難を伴いますが、適切な賠償を受けるという点においても等級に認定されるのか、どの等級で認定されるのかで大きく賠償額が異なります。
お悩みの際にはお気軽に弁護士にご相談ください。

-
【千葉法律事務所】
所属弁護士:大﨑 慎乃祐(おおさき しんのすけ)- プロフィール
- 専修大学法学部法律学科卒業、専修大学法科大学院法務研究科修了。弁護士登録以降、ご依頼者様のトラブル内容に対し、解決するための法的根拠や理由を丁寧に分析し、しっかりした主張を展開して解決に導けるよう、交通事故や一般民事、刑事事件などの分野で活動を行う。趣味はサッカーやジョギング、好きな言葉は「文武両道」。