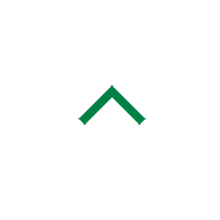2025年2月号: 高年齢者雇用安定法の継続雇用制度について
-

- L+PRESS 2025年2月 PDFで見る
高年齢者雇用安定法の継続雇用制度について
令和3年4月に改正された高年齢者雇用安定法により、従業員の定年年齢を65歳未満としている事業主に、
①定年制の廃止
②定年年齢の65歳までの引き上げ
③希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
のいずれかの措置(高齢者雇用確保措置)を実施することが義務付けられました。なお、当分の間、60歳以上の従業員が生じない企業であっても、いずれかの措置を講じなければなりません。高齢者雇用確保措置を講じていない企業は、企業名の公表やハローワークでの求人の不受理・紹介留保、助成金の不支給等の措置を受けることがあります。
高齢者雇用確保措置のうち、③継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者を本人の希望によって、定年後も引き続き雇用する制度であり、具体的には、再雇用制度(定年でいったん退職とし、新たに雇用契約を結ぶ制度)や勤務延長制度(定年で退職とせず、引き続き雇用する制度)があります。この制度には、労使協定により対象者を年齢により限定することができるという経過措置が認められていますが、令和7年3月末に経過措置が終了します。そのため、令和7年4月からは、継続雇用制度の導入措置を実施している事業主は、定年を超えても働きたいと希望する従業員全員を65歳まで雇用する義務を負うことになります。
もっとも、心身の故障のために業務に耐えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等の就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢に係るものを除く)がある場合には、従業員を継続雇用しないこともできます。継続雇用しないという判断は、事業主の主観ではなく、客観的に合理的な理由があり、社会的通念上相当であることが求められます。
また、継続雇用制度は、定年前と同じ労働条件や定年退職者である従業員の希望に合致した労働条件で雇用継続することを義務付けているわけではありません。賃金、勤務日・勤務時間等の見直しも可能であり、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を従業員に提示していれば、事業主と従業員の間で労働条件の合意が得られず、結果的に従業員が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反とはなりません。
高齢者雇用確保措置は主として期間の定めのない従業員を対象としていることから、有期雇用従業員(パートタイマー、アルバイト等)には基本的には適用されません。ただし、反復継続して契約の更新がなされているときには、期間の定めのない雇用とみなされることがあります。この場合には、一定の年齢に達した日以降は契約の更新をしない旨の定めが定年の定めと解されることがあるため、高年齢者雇用安定法違反とならないよう対応が必要となります。

-
【かしま法律事務所】
所属弁護士:齋藤 碧(さいとう みどり)- プロフィール
- 山形大学人文学部総合政策科学科卒業、大阪大学大学院高等司法研究科修了。主に、交通事故、労災事故、債務整理、過払い金回収、相続、離婚・不貞問題、中小企業法務(労務問題)を中心に、法的な問題でお困りの方の手助けができるよう活動を行う。趣味は植物を育てること、読書、音楽鑑賞、好きな言葉は「地に足をつける」。
被相続人の生前の預金引出しを追及されて訴訟提起されたが、抗弁事実を積み重ねて立証を尽くし、当方の全面勝訴で解決した事案
ご依頼者は被相続人の甥でした。ご依頼者の母(以下「Aさん」といいます。)が被相続人の面倒をみて、Aさんが被相続人から生前の財産の管理も任されていました。そして、ご依頼者はAさんをサポートする形で被相続人の面倒をみていました。
被相続人がお亡くなりになり、またすぐにAさんもお亡くなりになりました。
その後、ご依頼者は、被相続人の法定相続人(以下「相手方」といいます。)から、ご依頼者が被相続人の生前に引き出した預金約3900万円を返せと追及されたことから、どうすればよいのか相談に来られました。
活動の概要
本件では、ご依頼者が被相続人から委任状を取り付けたうえで約3900万円を引き出したことを証明する直接証拠がありました。加えて、引き出し後の現金が他の金融機関に入金されていたりしなかったため、現金のその後の行方が客観的にわかりませんでした。この点、預金を引き出した人がその後現金を管理していると推認されることが一般的であることから、ご依頼者は極めて不利な状況に立たされていました。
他方で、ご依頼者のお話しによると、預金の引き出しを行ったのは自身であるものの、引き出し時にはAさんも一緒におり、引き出し後すぐにAさんに全て渡し、その後はAさんが現金管理していた旨のお話しでした。
そこで、当職は、ご依頼者のお話を法的に構成するために、ご依頼者の現金管理を否定し得る証拠、Aさんが現金を管理していたことを推認し得る証拠、ご依頼者は普段からAさんをサポートする形で被相続人の面倒をみていたにすぎず預金の管理権限がない事実を推認する証拠収集を行っていきました。そのうえで、収集した第三者機関への調査結果、被相続人やAさんが残していた手帳、メモ、領収書等あらゆる客観的証拠を精査して、相手方の請求を全面的に争っていきました。
活動結果
結果として、第一審及び控訴審ともに相手方の請求は全部棄却され、当方の全面勝訴で事件を終了させることができました。
ご依頼者に不利な直接証拠がありながらも全面的に勝訴できたポイントとしては、直接証拠自体を争うのではなく、直接証拠から証明される事実を前提としたうえで、その事実と両立する新たな事実を推認する証拠を粘り強く積み重ねていったことにありました。
最後に
今回紹介した事案は、預金引き出しを追及される立場の代理活動です。預金引き出しを追及する立場なのか追及される立場なのかによって、また、同じ事件類型でも事案によって個別具体的に法的構成や主張・立証の程度を考えていかなければなりません。
弊所は、相続案件及び相続派生紛争案件を多く取り扱っております。
お困りの方はお気軽に弊所までお問い合わせいただければと思います。

-
【東京法律事務所】
所属弁護士:神津 竜平(こうづ りゅうへい)- プロフィール
- 國學院大学法学部卒業、明治大学法科大学院修了。弁護士登録後は主に、交通事故、労災事故、相続、中小企業法務(労務問題)を中心に、ベストな解決は如何なるものかを考え抜き、具体的に方針や見通しをお伝えした上で、ベストな解決を追求すべく活動を行う。趣味は旅行、釣り、好きな言葉は「人生一度きり」。