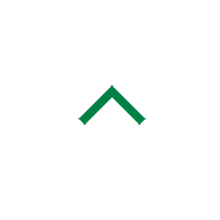2025年3月号: 労働時間管理の実務と法的留意点
-

- L+PRESS 2025年3月 PDFで見る
労働時間管理の実務と法的留意点
働き方改革に伴う労働時間の上限規制について、昨年4月より、それまで猶予されていた建設・運送業界にも適用されることになりました。
そこで、今回は労働時間管理について改めて取り上げます。
令和6年4月から適用されることになった建設業・運送業の労働時間の上限規制の概要を教えてください。
A 建設業では、時間外労働の上限は月45時間・年360時間です。ただし、年720時間までは例外が認められています(この場合も、2~6カ月の平均で月80時間まで、1月100時間まで、月45時間を超えられるのは年6回まで、という制約があります。)。
運送業も、上限月45時間・年360時間は変わりませんが、年960時間までは例外が認められています。なお、厚生労働大臣の告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」があり、1日の拘束時間は13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間とすること、拘束時間は年3300時間以内、月284時間以内とすること、1日の休息時間について11時間を基本とし、9時間を下回らないこと、運転時間は2日平均1日9時間以内とすることとされています。
路線バスを運行しています。始発バス停での出発前、待機中は休憩扱いとしていますが、乗客が来た場合には対応するよう指導しています。労働時間に当たるのでしょうか。バス停以外の場所で待機している場合はどうでしょうか。乗客対応はありませんが、稀にバスを移動させるよう言われることがあるようです。
A 乗客対応の義務があれば労働時間と考えます。
乗客対応の義務がないのであれば、労働時間になりにくいと考えますが、バスを動かさなければならない状況が相当の頻度で発生するためバスを離れられないといった事情があれば労働時間となる可能性が高いです(参考 福岡高裁令和5年3月9日、大阪高裁平成29年9月26日)。
事業場外みなし労働時間制についての最高裁令和6年4月16日判決の概要を教えてください。
A 外国人技能実習生の指導員に事業場外みなし労働時間制の適用があるか争われた事件です。九州各地を回り、臨時のトラブル対応も行っていました。直行直帰で携帯電話等による指示もありませんでしたが、高裁は、業務日報が作成されており、日報の正確性は指導員の相手方(実習実施者)に確認することで正確性が担保されていたこと、日報に基づき残業代を支払っていたこと等を理由とし、労働時間を算定しがたいとはいえないとしました。
しかし、最高裁は、日報の正確性を実習実施者に確認するといってもその現実的な可能性や実効性が不明で、日報のみを重視したのは誤りとして、審理をやり直すよう差し戻しました。差し戻しですから、これによって最高裁が新たな考え方を示したものではありません。差し戻し審での高裁の判断が待たれます。

-
【成田法律事務所】
所属弁護士:宮崎 寛之(みやざき ひろゆき)- プロフィール
- 中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院修了。日弁連裁判官制度改革・地域司法計画推進本部委員。平成29年度千葉県弁護士会常議員。主に、交通事故、労災事故、相続、離婚・不貞問題、債務整理、中小企業法務(労務問題)を中心に活動を行うと共に、千葉県経営者協会労務法制委員会等の講演の講師も務める。
交通事故解決事例
Aさんは、個人で運送業を営んでいる個人事業主です。自己所有の自動車で配達をしていたところ、追突されてしまい、頚椎捻挫・腰痛捻挫の怪我を負ってしまいました。
交通事故による怪我で思うようにお仕事をすることができず、その分の減収の補償に不安があり、ご相談に来られました。
1 休業損害の金額の計算方法
休業損害は、事故により減収が生じたことを前提として、原則、「基礎日額(1日あたりの賃金額)×休業日数」で計算されます。
雇用されて給与を受け取っている、いわゆる給与所得者の方であれば、事故前3か月分の給与を稼働日数又は90日で割って、休業損害の計算に必要な基礎日額を出すことができます。
個人事業主の方の場合には、事故前の確定申告書の収入額と事故後の確定申告書の収入額を比較して減収した分を休業損害と計算することができます。
しかし、休業期間を含む期間の確定申告書を取得できるのがかなり先になったり、休業期間と確定申告の対象期間にずれが生じる等の理由で、単純に減収分を比較できない場合があります。
その場合には、給与所得者の方と同じように所得金額と固定経費の金額から、基礎日額を算出して休業損害を主張していくことになります。
2 解決までの経緯
Aさんは事故の約1年前から個人事業主になったこともあり、事故前の確定申告書には、Aさんが給与所得者として働いていた時期の収入と個人事業主になった後の収入が混在しており、事故後の確定申告書には、一部事故後の収入が含まれている状況でした。そのため、確定申告書を見ても、Aさんの個人事業主としての純粋な減収金額が分からない状態でした。
そこで、Aさんの基礎日額を決めるべく、数カ月分しかない前年度収入は、その期間の日数で割って、1日の収入額を計算しました。
また、事故と同年度の収入に関しては、事故の前月までの収入額と、そこまでで均等割り付けした固定経費を足して、事故前までの期間の日数で割って、1日の収入を計算しました。
そして、事故の前年度年収における1日の収入額と事故と同年度の事故前までの1日の収入額の平均を、Aさんの基礎日額として計算しました。
なお、Aさんの休業日数は、実通院日数として計算し、Aさんは計算通りの休業損害を受け取ることができました。
3 おわりに
Aさんのように、個人事業主の方の場合、休業損害の計算が複雑になってしまう場合があります。
相手方保険会社からの賠償の提案が適正なものであるかご不安がある方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

-
【成田法律事務所】
所属弁護士:常世 紗雪(とこよ さき)- プロフィール
- 中央大学法学部法律学科卒業、一橋大学法科大学院修了。弁護士登録後は成田法律事務所に所属し、主に、交通事故、労働事件、離婚・不貞問題を中心に活動を行う。コミュニケーションを疎かにせず、ご依頼者様に心からご納得・ご理解いただけるように説明することを心がけている。好きな言葉は「進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む」。