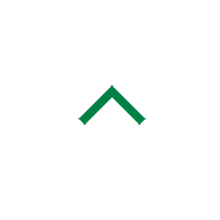2025年4月号: 相続登記の義務化に対する対応方法について
-

- L+PRESS 2025年4月 PDFで見る
相続登記の義務化に対する対応方法について
1.はじめに
2024(令和6)年4月1日から相続登記が義務化されました。義務化を知った方から、放置していた遺産分割を急いでまとめなければ、というようなご相談を受けることがありますが、制度上、拙速に遺産分割をまとめる必要はありません。
そこで、今回は、制度の概要説明と義務の履行方法についてご説明します。
2.相続登記の義務化
(1)義務の内容
相続登記の義務化とは具体的に次の対応を行うことです。
- 不動産所有者の相続が開始した場合に、相続又は遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
なお、相続発生が義務化された令和6年4月1日より前の場合、申請期限は、令和9年3月31日まで。 - 遺産分割(相続人間の話合い)によって法定相続分を超える所有権を取得した相続人は、当該遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記の申請をしなければならない。
(2)義務違反時のペナルティ
「正当な理由」がないのに上記①②の義務を履行しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。義務を履行しないと、登記官から催告書が届くことがあります。その後も必要な対応を取らない場合に過料が科せられることがあります。
(3)義務を履行しなくてもよい「正当な理由」とは
相続登記等を行わなくても過料のペナルティを負わないとされる「正当な理由」は次のようなものが該当するといわれています。
- 相続人が極めて多数で、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
- 相続に関して、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
- 相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- 相続登記等の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
- 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮して費用負担ができない場合
3.相続登記の義務を履行するための簡易な方法
(1)相続人申告登記
相続登記は、3年の期間制限ですが、相続人間の遺産分割協議がまとまらない場合等、正当な理由が無くても、相続登記等の実施が難しい場合があるかもしれません。
そういう場合に、簡易に義務を履行できる制度として、「相続人申告登記」というものがあります。期限内に、相続人申告登記を行うことで、義務を履行したこととなり、過料のペナルティを回避できます。
(2)手続き方法
法務局に対して、対象となる不動産に関して、申請者が所有者の相続人であることを示す戸籍等を準備の上、次のことを書面で申し出ます。費用は掛かりません。
- 所有権の登記名義人について相続が開始したこと
- 自らがその相続人であること
4.さいごに
相続登記が義務化されましたが、簡易な義務履行方法(相続人申告登記)を活用することもできますので、義務化に左右されずに遺産分割の協議を進めていただければと思います。

-
【東京法律事務所】
所属弁護士:藥師寺 孝亮(やくしじ こうすけ)- プロフィール
- 早稲田大学商学部卒業、日本大学法科大学院修了。民間企業に勤務していたが、一念発起して弁護士を目指す。現在は東京法律事務所に所属し、主に相続を中心に活動を行う。「ご相談者様・ご依頼者様に笑顔を取り戻してもらいたい。」という思いを大切に、少しでも良い未来に向かっていただけるよう、知恵を絞り、行動するよう心がけています。好きな言葉は「人事を尽くして天命を待つ」。
交通事故解決事例
1.相談までの経緯
会社員であるⅩさんは、信号のない交差点の横断歩道を歩いて渡っていたところ、走行してきた相手方車両と衝突し、左腕の骨折などの怪我を負いました。幸いにも後遺障害は残りませんでしたが、Xさんは1年以上の通院を余儀なくされました。治療終了後、Xさんは、相手方保険会社から提示された損害額の計算書をみて、当初は慰謝料額が適正なものか確認するためご相談にいらっしゃいました。
2.相談時のヒアリング
Ⅹさんの怪我の程度や治療期間をふまえると、たしかに保険会社の提示してきた慰謝料額は低額なものとなっていました。
しかし、さらに計算書中の他の項目を確認したところ、休業損害についてはゼロとされていました。弁護士がXさんに確認したところ、「減給がないから休業損害は発生していないと思う」とのご回答でした。しかし、さらに話を聞くと、減給が生じなかったのは、Xさんが有給休暇を利用して通院をしていたためと判明しました。
3.有給休暇と休業損害
たしかに、有給休暇を利用すれば減給が生じることはなく、休業損害は請求できないとも思えます。しかし、有給休暇は本来いつ何のために使用するか自由なはずであり、交通事故に伴う通院のためにこれを消費せざるを得なかったという点で、一定の不利益が生じているといえます。このことから、有給休暇を使って通院を行った場合にも、欠勤した場合と同様、日数に応じた休業損害を請求できると考えられています。
なお、有給休暇の中でも、使途を限定した傷病休暇などを利用した場合には、いつ何のために使用するか制限があるという点で通常の有給休暇と異なり、休業損害の対象とはならないとされています。
4.受任後の経緯
Xさんが通院のために有給休暇を使っていた事実を客観的に証明するため、Xさんの勤務先に休業損害証明書の作成を依頼しました。同時に、収入の裏付け資料として、Xさんからも源泉徴収票などの提供をお願いしました。これらの資料をふまえて弁護士においてXさんの休業損害額を計算し、慰謝料額も適正なものに修正したうえで保険会社と交渉を開始しました。
結果、慰謝料額もあわせて、当初の提案額から3倍以上の増額に成功し、示談することができました。
5.おわりに
交通事故に遭った場合、被害者の側から相手方保険会社に休業が生じている旨を申告すれば、保険会社から休業損害証明書の書式などが渡されます。しかし、相手方保険会社はあくまで損害を支払う立場である以上、自主的に被害者の事情をどこまで聞き取ってくれるかは、保険会社のさじ加減となります。今回のケースでも、実際には休業損害が発生しているにもかかわらず、「減給はない」との回答のみから、休業損害がないと安易に扱われたものと思われます。
実態にそぐわない内容でも、一度示談をしてしまうと後戻りができなくなります。少しでも気になる点がございましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

-
【柏法律事務所】
所属弁護士:宇野 浩亮(うの こうすけ)- プロフィール
- 一橋大学法学部法律学科卒業、一橋大学法科大学院修了。弁護士登録後は柏法律事務所に所属し、主に、交通事故、労働事件、相続、離婚・不貞問題、中小企業法務(労務問題)を中心に活動を行い、ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、信頼される関係をしっかりと構築しながら解決に向けた活動を行う。好きな言葉は「一期一会」。